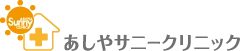ヘルパンギーナ|夏に流行する子どもの発熱・口内炎の感染症
ヘルパンギーナは、乳幼児を中心に夏季に流行するウイルス感染症です。
突然の高熱と、のどの奥(軟口蓋や咽頭後壁)にできる小さな水疱や潰瘍が特徴で、痛みにより食事や水分がとりにくくなることもあります。
多くは数日で自然に回復しますが、脱水症状を防ぐことが重要です。
当院では症状に応じた診察・対処を行っています。
最初にまとめ
感染
病原体は、主にコクサッキーウイルスA群で、年によって流行する型が異なることがあります。
まれにエンテロウイルス属の他の型も原因となることがあります。
主な感染経路として、
感染経路
などが知られています。
感染後糞便中には2~4週間ウイルスが排泄されると考えられています。
感染の傾向として、
といった特徴が挙げられます。
なお、ヘルパンギーナは乳幼児を中心に流行する感染症ですが、成人に感染することもあります。
成人コミュニティで流行することは殆どありませんが、感染したお子さまからうつるものと考えられ、小さなお子さんと接する機会の多い保護者や保育関係者では注意が必要です。
高熱や咽頭痛が主症状で、子どもよりも症状が強く出ることもあります。
症状
2〜4日間ほどの潜伏期間を経て、以下のような症状を認めます。
主な症状
喉の痛みから経口摂取不良を呈することがあり、そういった場合は脱水にならないよう注意しましょう。
また、倦怠感や下痢などを伴うこともあります。
皮膚の症状や粘膜の症状をそれぞれ皮疹・粘膜疹といいます。
教科書的にはヘルパンギーナは皮疹を伴いませんが、臨床的には皮疹を伴うことがあり、手足口病との見分けがつきにくいことがあります。
皮疹の傾向として、
といった傾向があります。
色々手足口病と似ているところがありますが、口内病変について、手足口病は口腔内のどこにでも生じやすい一方、ヘルパンギーナは、口蓋垂の両脇(下図の丸印)に生じやすいという傾向があります。

診断
インフルエンザのような迅速検査キットなどはなく、
するのが一般的です。
保育園・幼稚園・学校内、あるいは家庭内での発生状況は有用な情報になります。
成人の感染もあるため、親御さんの「そういえば口内炎があるかも」といった情報が有用な場合もあります。
水疱を形成する点などから、手足口病・水痘(水ぼうそう)・単純疱疹などとの見分けが必要です。
治療
ヘルパンギーナに対しては、インフルエンザのような特効薬(例:タミフル®など)はなく、発熱や咽頭痛に対する対症療法が中心となります。
のどの痛みにより水分や食事がとりにくくなることがあるため、脱水予防として、水分摂取の励行に努めましょう。
重症例や合併症はまれであり、ほとんどは数日で自然に回復します。
学校保健安全法による登園・登校の規定
本法による登園・登校停止の規定はなく、解熱していて全身状態良好なら登園・登校は可能です。
FAQ(よくあるご質問)
ヘルパンギーナは法律で登園・登校停止が定められている感染症ではありません。
ただし、発熱やのどの痛みなどが改善し、普段通りに食事・活動できるようになってからの再開が望まれます。
園や学校によっては独自の判断を求める場合もあるため、念のため確認しておくと安心です。
どちらもエンテロウイルス属による夏季のウイルス感染症ですが、主な違いは以下の通りです:
- ヘルパンギーナ:突然の高熱+のどの奥の水ぶくれが中心。皮疹はまれ。
- 手足口病:軽度の発熱+口・手・足・お尻の発疹が特徴。
いずれも自然に治癒することが多いですが、脱水などに注意が必要です。
ヘルパンギーナはウイルス感染症のため、抗菌薬(抗生物質)は無効です。
現在、ウイルスを直接抑える特効薬はなく、解熱や痛みの緩和、脱水予防などの対症療法が基本です。
はい、大人にもうつることがあります。特に保育士・看護師・保護者など、子どもと接する機会の多い方が感染するケースがあります。
子どもよりも強いのどの痛みや高熱が出ることもあるため、無理せず受診・休養をとってください。
ヘルパンギーナは複数の型(血清型)があり、1度かかったあとでも別の型に感染することがあります。
ただし、2度目以降は症状が軽く済むことも多いです。