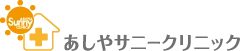新型コロナワクチン
新型コロナウイルス感染症は、発熱や咳などの症状を起こし、ときに肺炎などの重い経過をたどることがあります。
高齢の方や基礎疾患をお持ちの方では重症化のリスクが高く、注意が必要な感染症です。
当院では、新型コロナワクチンの予防接種を実施しています。
本ページでは、ワクチンの種類や仕組み、接種制度(定期接種・任意接種)などについてわかりやすくご案内します。
最初にまとめ
新型コロナワクチンとは
新型コロナワクチンは、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2) に対する免疫をあらかじめつくり、感染した際の発症や重症化を防ぐことを目的としたワクチンです。
新型コロナウイルスは、その表面に「スパイクタンパク」と呼ばれる特徴的な構造を持っており、新型コロナワクチンは、このスパイクタンパクを標的としています。
スパイクタンパクに対する免疫誘導を惹起するためには、体内で免疫系に対してスパイクタンパクを抗原として提示する必要があります。
外部から抗原を投与するという方法は、これまで様々なワクチンで使用されてきたものですが、開発に時間を要するだけでなく、製造自体も時間を要するもので、世界規模のパンデミックという局面ではより迅速性に秀でた方法が求められました。
そんな中、免疫学的な癌の治療法として開発中だったmRNAワクチンにスポットライトが当たりました。
mRNAワクチンは外部から抗原ではなく、抗原の設計図(遺伝子情報)を投与し、抗原は被接種者自身に産生させるという手法です。
開発の観点からは、抗原の遺伝子情報さえわかれば速やかに設計が可能で、製造の観点からは、培養という手順がないことから製造が速やかかつ、バイオセーフティ施設を必要としないというメリットがあります。
癌治療においてはがん細胞の遺伝子情報の多様性が開発を難航させましたが、遺伝子情報の均一性が高い感染症は開発しやすく、世界的なパンデミックという迅速性が求められた局面が特性とマッチし実用化に至りました。
一方でスパイクタンパク(抗原)を外部から投与する方法の開発も進められ、B型肝炎ワクチンやHPVワクチンで実績のある組み換えタンパクワクチンの新型コロナワクチンも実用化に至っています。
現在国内で接種可能な新型コロナワクチンについて整理しておきます。
これらのワクチンの接種により、免疫系がスパイクタンパクを異物として認識し、抗体や記憶細胞(免疫記憶)が形成されます。
その後、実際にウイルスに感染しても、体内の免疫系が迅速に反応してウイルスの増殖を抑え、発症や重症化を防ぐことができます。
発症や重症化のリスクは、ワクチンの種類や接種回数(特に新しい株に対応したものかどうか)、接種からの経過時間、基礎疾患の有無、暴露したウイルス量など、さまざまな要因によって変わります。
そのため、接種を受けたすべての方が発症しない・重症化しないわけではありませんが、ワクチンによってこれらのリスクを下げることができると考えられています。
新型コロナワクチンのメリットとデメリット
新型コロナワクチンは、mRNAという新規のワクチン技術を用いた初めての実用化例であり、一部に特異的な副反応が報告されたことから、社会的にも一定の警戒感をもって受け止められました。
以下では、国内外の研究や公的データに基づき、ワクチンのメリットとデメリットをまとめます。
メリット(期待できる効果)
デメリット・注意点(副反応と限界)
メリット(期待できる効果)
重症化・死亡のリスクを大幅に減らします
入院や重症化を防ぐ効果が持続します
感染後の「後遺症(Long COVID)」を減らす可能性があります
医療逼迫やクラスター発生の抑制にも寄与
デメリット・注意点(副反応と限界)
接種後の一時的な副反応があります
まれに心筋炎・心膜炎などの報告があります
感染予防効果は数か月で弱まります
追加接種の必要性は人によって異なります
出典
- 厚生労働省「新型コロナワクチンの有効性・安全性について(2024年)」
- 国立感染症研究所(NIID)感染症疫学センター
- CDC MMWR 2024; 73(15):430–439
- WHO “COVID-19 vaccines: safety and effectiveness summary.”(2024)
- Lancet Infect Dis. 2024; 24(4):421–431(DOI:10.1016/S1473-3099(24)00015-2)
- Lancet Respir Med. 2023; 11(5):435–447(DOI:10.1016/S2213-2600(23)00045-9)
- Nature Med. 2024; 30(2):205–213(DOI:10.1038/s41591-023-02813-6)
- NEJM. 2022; 387:1813–1823(DOI:10.1056/NEJMoa2208350)
- JAMA Cardiol. 2022; 7(5):500–512(DOI:10.1001/jamacardio.2022.0001)
- Nature Med. 2023; 29:213–225(DOI:10.1038/s41591-022-02162-1)
接種の種類
初回接種と追加接種
新型コロナワクチン未接種者が、免疫能を獲得するために行う接種を「初回接種」といい、既に初回接種を済ませた方が、時間経過とともに低下した免疫能を高めるために行う接種を「追加接種」といいます。
すでに2回以上接種が済んでいる場合は、今後の接種は追加接種となります。
初回接種
追加接種
なお、定期接種対象者が初回接種である場合、2回接種のうちの1回は定期接種、残りの1回は任意接種として取り扱われます。
定期接種と任意接種
ワクチン接種には、主に公衆衛生上の重要性から以下のような区分があります。
定期接種
任意接種
この他に緊急性のある非常事態において実施される臨時接種や特例臨時接種といったものがあります。
新型コロナウイルス感染症の発生初期に新型コロナワクチンは特例臨時接種として迅速かつ、高い接種率の向上が図られ、2024年4月1日からは現行の実施体制となりました。
新型コロナワクチン定期接種の対象者の概要は以下の通りです。
定期接種の対象者
定期接種の詳細は以下からご確認下さい。
外部リンク
FAQ(新型コロナワクチンについてよくある質問)
mRNAワクチンは、ウイルスそのものではなく「抗原(スパイクタンパク)」の設計図を体内に送り込み、体の細胞にその抗原を一時的に作らせることで免疫を誘導する仕組みです。
これまでの「不活化ワクチン」や「組換えタンパクワクチン」と違い、遺伝子情報を利用して抗原を作らせる点が特徴です。ワクチンに含まれるmRNAは体内で速やかに分解され、DNAに組み込まれることはありません。
mRNAワクチンは確かに新しい技術ですが、長年がん免疫治療などで研究されてきた技術を応用したものです。
新型コロナワクチンとして世界で数十億回接種された実績があり、重篤な副反応はまれであることが確認されています。
国内外のデータから、発症・重症化・死亡のリスクを減らす効果が副反応のリスクを上回ると考えられています。
ごくまれに、mRNAワクチン接種後に心筋炎・心膜炎が起こることがあります。特に若年男性でやや多い傾向が報告されていますが、ほとんどが軽症で自然回復する例です。
なお、新型コロナウイルス感染そのものでも心筋炎は起こり得るため、感染を防ぐことで心筋炎全体のリスクを下げるという見方もあります。
また、mRNA以外のワクチン(組換えタンパクワクチンなど)も選択肢として認められています。
新型コロナワクチンは発症や重症化を減らすことが目的であり、感染そのものを完全に防ぐものではありません。
感染すること自体はありますが、接種を受けていると症状が軽くすむ、入院や死亡のリスクが低下することが多くの研究で示されています。
特に高齢者や持病のある方では、ワクチン接種のメリットが大きいとされています。
ウイルスの変異によって、ワクチンの「感染・発症を防ぐ力」は変動します。
しかし、重症化を防ぐ効果は一定程度維持されていることが確認されています。
最新のワクチンは流行している株(例:オミクロン系統など)に合わせて設計されており、定期的な接種で免疫を保つことが大切です。
接種のメリット(重症化予防・後遺症予防)と、まれな副反応のリスクを総合的に考えることが大切です。
特に高齢者・基礎疾患のある方・妊娠中の方では、ワクチンによるリスク低減効果が明確に確認されています。
接種の可否は、年齢・健康状態・これまでの接種歴を踏まえて医師にご相談ください。
新型コロナワクチンのご予約について
原則的にWEB予約にて承っています。
WEB利用が不慣れな場合は電話予約をご利用下さい。