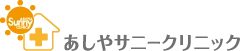📝医療コラム:風邪の診療シリーズ①
― かぜ症候群の種類について ―
はじめに
「風邪っぽい」「風邪をひいたかも」。
誰もが経験する風邪は、日常の中でごく自然に使われる言葉です。
ところで、「風邪」とは本来どのような病気なのでしょうか?
私たち医療者は、それをどのようにサイエンスとして捉えているのでしょう。
この医療コラムでは、「風邪の診療シリーズ」の第1回として、「そもそも風邪とは?」について、当院の診療スタンスも交えてご紹介します。
実は「風邪」という病気はない!?
医学の教科書には「風邪」という名前の項目は基本的に登場せず、あっても「かぜ症候群」という形で紹介されています。
しかしこの「かぜ症候群」も、執筆者によって定義にばらつきがあり、疾患概念としてしっかり確立されているとは言い難いのが実情です。
医師に「風邪とは何か?」と尋ねたとしても、その答えは人によって異なるでしょう。
それでも、医師は「風邪ですね」と言う
それでも診察の現場では、医師から「風邪ですね」と伝えられる場面が日常的にあります。
多くの医師は、
「何らかの感染症により、鼻やのどの症状、咳などを呈しているものの、重症化リスクが低く、検査や入院を要しない状態」
と判断したときに、「風邪ですね」と表現しているように思います。
私自身は、
「鼻やのどの不調、咳、微熱などを認める、比較的軽症の呼吸器感染症(ただし肺炎などは除く)」
という状況で、この言葉を用いています。
いずれにせよ、「風邪」という言葉はあいまいさを含んだ用語であり、“かぜ症候群”とは多くの意味で“ぼんやりとした概念”であるのが実情です。
私自身、診断名としては「急性副鼻腔炎」「急性咽頭炎」「急性扁桃炎」「急性喉頭炎」など、より具体的な疾患名を用いることも少なくありません。
一方で、患者さんが聞き慣れない専門用語に戸惑わないよう、あえて「急性上気道炎」や「風邪」といった一般的な表現を選ぶこともあります。
学術的な引用から紐解く
米国内科学会の見解の一つ
2001年、米国内科学会(ACP)が「急性気道感染症」に関する整理を発表しています。
これは、臨床上のかぜ症候群の考え方に近いものとされ、現在も参考になる分類です。
その中では、症状の出方によって以下のように分類されています:
| 急性気道感染症 | 症状 |
|---|---|
| 非特異的上気道炎 | 鼻水・鼻づまり、のどの痛み、咳・たんのいずれも同等に認める |
| 急性鼻炎・急性副鼻腔炎 | 鼻水・鼻づまりが主体 |
| 急性咽頭炎・急性扁桃炎 | のどの痛みが主体 |
| 急性気管支炎 | 咳・たんが主体 |
「気道」とは、呼吸器の空気の通り道のことで、鼻・咽頭・喉頭などの上気道と、気管・気管支などの下気道に分けられます。
上気道に生じる急性の感染症が「急性上気道炎」と呼ばれ、それらを広くまとめて「かぜ症候群」と呼ぶケースもあります。
米国内科学会の分類は、肺を除く気道の感染症を急性気道感染症という症候群としてまとめていることが分かります。
国内の見解との齟齬
日本国内では、治りやすさや病態の明確さを重視し、急性副鼻腔炎や急性扁桃炎などをかぜ症候群に含めないことがあります。
また、「かぜ症候群=急性上気道炎」とする見方が主流である一方、下気道に生じる軽度な急性気管支炎などを含むこともあります。
私自身は概ね米国内科学会の急性気道感染症の考え方に同意しつつ、急性気管支炎は「気管支炎という胸の中のお風邪」と表現することがあります。
あしやサニ―クリニックとしては、「急性気道感染症が“かぜ症候群”の実体に近い」と考えており、今後のコラムでもこの見解をもとに解説を続けていきます。
まとめ
今回はここまでです。
風邪の分類についてご紹介しましたが、「なんとなく分かりにくい」と感じられた方もいらっしゃるかもしれません。
でも、それが“風邪らしさ”なのです。
誰もがかかる風邪。
その実態は医師でさえ一言では語りきれない、奥深く多様なものです。
次回のコラムでは、「風邪の症状」について、もう少し具体的に整理していきます。
▶ 次回予告:「症状は風邪の大事な情報です」