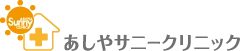概要
インフルエンザにかかったので「もう接種する意味はなくなったでしょうか?」というお問い合わせをしばしば頂きますので本ポストにて解説致します。
インフルエンザウイルスには種類があります
新型コロナウイルスは当初武漢株対応で始まり、アルファ株・デルタ株・オミクロン株など遺伝子変異によって何種類ものバリエーションが生じたのは記憶に新しいところです。
インフルエンザもご存知の通りA型・B型という異なる遺伝子型があり、それぞれにさらなる遺伝子型のバリエーションがあります。
そして1シーズンでこれらのうち1つ、ないし複数が流行します。
例えばシーズン当初にA型が流行し、3月頃にB型が流行するというようなことがあります。
インフルエンザワクチンは4種類の遺伝子型に対応しています
実はインフルエンザワクチンはシーズン毎に中身が違います。
それはシーズン毎に流行する遺伝子型が異なるためで、春頃に流行する遺伝子型4種類を予測・決定し、それに基づいてワクチンが製造され始めます。
つまりインフルエンザワクチン接種を受けると4種類の遺伝子型に対する免疫応答能が高まることになります。
インフルエンザにかかると
インフルエンザにかかるとかかったインフルエンザウイルスの遺伝子型に対して抗体が産生されるなどして、シーズン中に同一遺伝子型ものに再感染する可能性は極めて低くなります。
ところが他の遺伝子型に対しては依然「丸腰」であり、シーズン中に他の遺伝子型の流行が始まると再び感染リスクに晒されることになります。
インフルエンザにかかって免疫応答能が高まるのはかかった1種類のみに対して、一方ワクチン接種では4種類に対してですのでインフルエンザにかかっても接種する意味がある訳です。